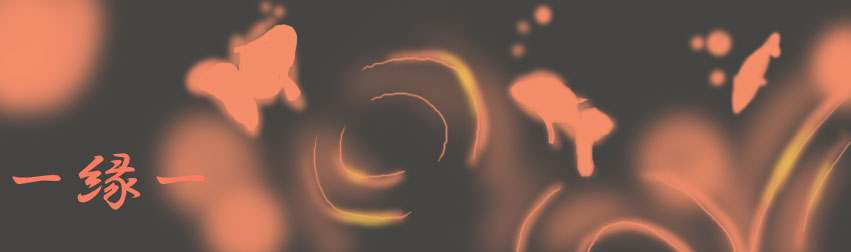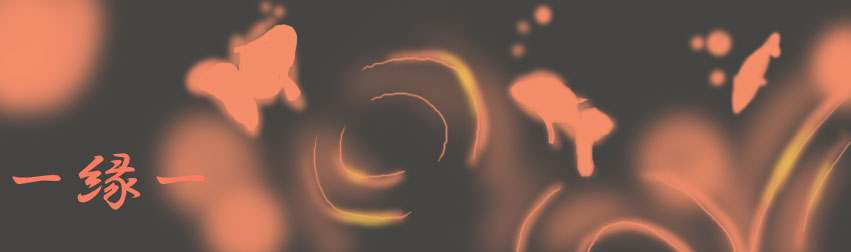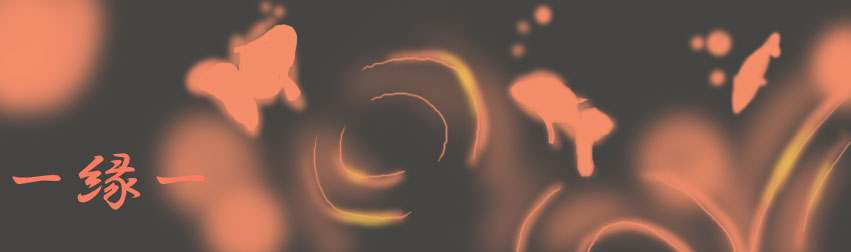あなたは私を1人の女と見てはくれない。
あなたの目に映る私はただのちっぽけな子供だから。
あなたにとって私は他の家族と同じ。
だから私はあなたを当主様とは呼ばない。決して。
小さな頃から夢を見ていた。
夢の中の私はいつもその身に鎧を纏い、この世の者なのかと想う様な禍々しい鬼達と戦っていた。
そしてその傍らにはいつも彼がいた。
長い青銀色の髪を後ろで束ね、涼やかで優し気な眼をした美しい顔立ちの少年だ。
その人の名は誠刃といった。
彼もまた時折青白くギラリと光る刀を握りしめ、鎧を纏う剣士だった。
夢の中の私達はいつも鬼達を倒すために戦いに赴いていた。
ある時は我が子を失い正気を失った天女を、ある時は天まで届きそうな高い塔の上に住まう風神雷神を、
ある時は鳥居の奥深く住まう美しい九尾の女狐を。
私達は共に笑い、共に泣き、共に語り合い、共に戦場を駆け抜けた。
夢の中の私達は日を追うごとに成長を遂げているようだった。
同じくらいで僅かに高かった私の背もいつの間にか誠刃に抜かされていた。
やがて私達はお互いを意識し、愛し合うようになっていた。
しかしある時彼は力尽き、死んでしまう。
私は彼の亡骸に誓いをたてる。
「たとえこの命尽きようとも、あなたの魂をきっと見つけ出して見せる。だから今は…どうか暫しの別れを…。」
私は冷たくなった彼の唇に口づけをする。
そして私の夢は途切れる。
だから生きているあなたに逢えた時は死ぬほど嬉しかった。
それがたとえ呪われた一族であったとしても…。
その時私が赤ん坊であなたの命の火がもう少しで消えてしまうとしても…。
私達の明日が戦いの中にしかなかったとしても———。
巻物や書物の積まれた部屋に、6月の梅雨の時期にしては久しぶりの明るく柔らかな日差しが差し込む。
天然のふわふわでクルクルした長い金色の髪が日の光を受けて眩しい程に輝く。
縁——少女はゆっくりと眼を開き、眩しそうに屋根から覗く空を眺めた。
どうやら書物を読んでいるうちに眠くなって寝てしまったようだ。
まだ頭がすっきりとしないが縁はふと辺りを見回す。
居た。
縁の視線の先刀を抱き、柱にもたれて眠っている男が1人…誠刃だ。
青銀色の髪が僅かに日にあたって美しくきらきらと輝いている。
女性と見紛う様な美しい顔立ちで眼を閉じたその姿は長い睫毛が強調されとても美しい。
縁は起き上がろうとして自分に誠刃の羽織がかけられていることに気付き、その羽織をそっと誠刃にかけ直す。
…がどうやら眼を覚ましてしまったらしい。
「ん…縁?悪いな…どうやらお前の顔を見ていたら眠ってしまったようだ…。」
「み…見てたの?」
「ああ。涎垂らして気持ちよさそうに…。」
縁は顔を真っ赤に染めて自分の口元に手をやった。
「もう!どこ見てるのよ!誠刃のバカバカ!」
縁は恥かしそうに誠刃をポカポカと殴った。
誠刃は笑いながら「痛い、痛い!」と言ったが、縁の両腕を掴んで一言。
「俺をバカにするのはお前くらいだよ、お姫様。」
…と言った。
縁は耳まで赤く染めた。
「もう!子ども扱いしないで。」
それでも誠刃が真っすぐと縁を見つめるので縁は目を逸らし呟いた。
「誠刃はずるい。私は覚えているのに誠刃は何も覚えていないんだもの。
私ばかり空回りして、バカみたいだわ。」
「縁?何だかよくわからないけど、俺はお前がバカだと思った事は一度もないぞ。」
…そういうと誠刃は縁の頭をポンポンと軽く撫でた。
「もうっ子ども扱いしないでっ」
「はははははっ」
誠刃は少年のように笑った。
その声に気が付いたのか、バタバタとこちらへ駆けてくる音が聞こえてきた。
イツ花だった。
イツ花はいつもの様な元気な笑顔と大きな声で誠刃と縁に声をかけた。
「お目覚めですか当主様、縁様!」
「ああ、少し疲れて寝ていたようだ。」
「ほお、珍しいですね。当主様がお昼寝とは…!」
「そうか?」
「はい。いつも気を張り詰めたようにする事はあっても、無防備とは言わないものの、お昼寝してるお姿なんて初めて見ましたよ!」
「…縁を見てると安心するんだ。何故だろうな。
それはそうと、何か用があったのではないのか?」
誠刃は訝しげにイツ花を見た。
イツ花は困った様に話始めた。
「…才様が…当主様をお呼びになっておられます~…。
恐らくは交神の件かと思われます。」
誠刃は「またか…」と小さな声で呟くと、渋々立ち上がり、眠っていた部屋を後にした。
縁は嫌な胸騒ぎがしてイツ花に尋ねた。
「イツ花…、誠刃は交神の事何か言ってた…?」
イツ花は慌てたように口に手を当てた。
「あ…いえ私は何も。そ…そういえば雪世様が縁様をお呼びになってらっしゃいましたよ?」
「え?雪世ちゃんが…?」
縁は慌てて雪世のもとへ駆け付けた。
雪世は縁の幼馴染であり、一族の中で縁の姉的な立場にいる人物である。
雪世の兄の真冬と縁は因縁の中ながら、雪世は縁の誠刃への想いを知る唯一の存在であり、いつも縁を優しく見守ってくれる存在である。
縁にとっては友の様な人…その雪世が、今にも泣きそうな顔で立ち尽くしていた。
「大丈夫?どうしたの雪世ちゃん…?」
「縁ちゃん、私、通りかかって聴いてしまったの…。
誠刃さまに…誠刃さまに…。」
「誠刃が…?」
「誠刃さまには想いを寄せる方がいらっしゃるみたいなの…。」
「え……?」
縁は頭が真っ白になった。
いつも子ども扱いされている縁にとって、誠刃が自分を女として見ていない事くらいわかっている。
たとえ前世で恋人同士だろうと、夢の中で結ばれようと、今の生で既に女と見られていない以上、縁には可能性なんて感じられなかった、それでも、それでも心のどこかで誠刃はいつか自分を選んでくれるかもしれない。
そんな望みを捨てきれなかったからだ。